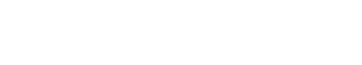着物の絞りとは?種類や知っておきたい特徴・見分け方

着物の中でも、独特の風合いや立体感で目を引くのが「絞り染め」です。伝統技法であり、繊細さと華やかさを兼ね備えた装いが完成します。
一口に絞りといっても、手作業で仕上げるものから機械による加工、さらには見た目だけを再現したプリントタイプまで多様な種類があります。
また、鹿の子絞りや有松絞りなど、地域や技法によっても名称や特徴が異なるため、選ぶ際にはその違いを把握しておくと、より着物を楽しめるでしょう。
この記事では、着物における絞りの基礎から代表的な種類、見分け方や魅力までを紹介します。
絞り染めについて知りたい人や、絞り染めの着物をこれから着たいと考えている人はぜひ参考になさってください。
着物の絞りとは?概要と代表的な着用シーン

絞り染めは、布を糸で縛って染料の浸透を抑えることで模様を生み出す技法です。古来より日本で発展してきた伝統的な染色法で、着物の世界でも高い評価を受けています。
ここでは、絞りの基本と代表的な着用例を紹介します。
着物の絞りの概要
絞りは布を縛ったり畳んだりして染め分ける技法で、模様を浮かび上がらせ、独特の風合いを生み出します。手作業によるものは一点ごとに風合いが異なり、ほかに同じものがない点が魅力のひとつです。
さまざまな絞り方がありますが、中でも鹿の子絞りや有松絞りなどが知られており、染め上がりのふくらみや陰影が美しい仕上がりになります。
布に残る細かな絞り跡もその価値の証とされており、工芸品としての評価が高い点にも注目です。
『総絞り』とは?
総絞りとは、着物全体に絞り染めを施した仕立てで、その緻密さと手間から高級品として扱われることが多いです。
生地全面に絞りが入っており、見た目にも柔らかく、布地がふっくらと浮き立つのが特徴です。
華やかでありながら繊細な印象を与え、格調高い場や式典にも適しており、年齢を問わず着用できるのも魅力です。
代表的な着用シーン
絞りの着物は華やかな場にふさわしい装いでありながら、柔らかく上品な印象も併せ持ちます。
とくに総絞りの一部は、格の高さから礼装としての扱いも受けており、帯や小物との組み合わせ次第で幅広いシーンに対応可能です。
ここでは、絞りの代表的な着用シーンについて見てみましょう。
袖が短い総絞り
袖丈の短い総絞りの着物は、小紋や訪問着として仕立てられることが多く、普段のお出かけや気軽な場面でも着用しやすい仕様です。
肩や身頃全体に絞りが施されていても、袖が控えめであることで落ち着いた印象になります。
とくに年齢を重ねた女性にとっては、華やかさと品のバランスを保ちやすい一着です。季節の催事などでの着用にも向いているでしょう。
袖が長い総絞り
袖丈の長い総絞りは、未婚女性の第一礼装である振袖として用いられることが多く、成人式や披露宴の主役として着用されます。
絞りによる立体感が袖の動きに合わせて豊かに表情を変え、場の雰囲気を華やかに演出します。
絞り染めが一面に施されていることで布の質感に重厚感が生まれ、振る舞いに品を添える効果もあるでしょう。
部分絞り
部分的に絞りが入った着物は訪問着に分類され、フォーマルな場面からカジュアルな場面まで幅広く対応でき、子どもの入学式・卒業式、お宮参りなど改まった席にもふさわしい装いです。
「部分」というと少々格が落ちるような印象があるかもしれませんが、そのようなことはありません。
むしろ利用シーンが多いため、さまざまな場所で着物を楽しみたい人におすすめです。
着物の絞りは3種類の作り方がある

絞り染めにはいくつかの工程があり、その作り方によって仕上がりの質感や価格帯が異なります。手作業による伝統的な技法や、現代の需要に合わせて効率化された方法などさまざまです。
ここでは、主に用いられる3つの技法について紹介します。
手絞り
手絞りは、職人が手作業で糸をかけて絞る伝統的な技法で、着物の絞り染めとして最も格式が高いとされています。
独特の立体感やふくらみが生まれ、染め上がりに温かみと深みが出る点が魅力です。
手間と時間がかかり、中には数年をかけて仕上げられるものもあります。その分、一点ものとしての希少性が高く、工芸品として評価されることも少なくありません。
機械絞り
機械絞りは手絞りの技法を再現するために開発されたもので、絞り部分を機械的に加工することで量産性を高めています。
見た目は手絞りに近く、全体の模様や風合いも一定の品質が保たれるため、日常使いの着物や比較的安価な商品に採用されることが多い方法です。
コストを抑えつつも、絞り染めの雰囲気を十分に楽しめるでしょう。
友禅絞り
友禅絞りは、絞りの模様を布に印刷する手法で、絞り染めの風合いを視覚的に再現しています。
実際には布を絞っていないため、立体感や凹凸はほかの技法よりも物足りなさがありますが、価格を抑えて絞りの柄を楽しめる手段として流通しています。
リーズナブルにさまざまな着物を楽しんでみたい人におすすめです。
絞りの種類や特徴

絞り染めには多様な技法があり、それぞれ異なる模様や風合いが生まれます。
日本各地で独自に発展した伝統技法も多く、技法名や地域名がそのまま絞りの名称になっている場合も少なくありません。
ここでは、代表的な絞りの種類と特徴を紹介します。
鹿の子絞り
鹿の子絞りは、小さな絞り粒を整然と並べて模様を作る技法で、全体が鹿の子模様のように見えることから名づけられました。
細やかな絞り跡が特徴で、総絞りの着物や晴れ着に多く使われています。
次の項から鹿の子絞りの種類を見てみましょう。
一目絞り
一目絞りは生地の線状に一粒ずつ絞った技法で、模様の輪郭を縁取る際や線を表す際に用いられます。
一粒に対して糸を2回巻いて括るのが特徴で、後述する疋田絞りや本疋田絞りと一緒に施されることも多いです。
絞った形状が人の目に似ていることから「人目絞り」と記されることもあります。
疋田絞り
疋田絞りは、一目絞りを整然と並べた鹿の子絞りの一種で、一粒につき綿糸を約4回巻いて括る技法です。「4回」は厳密な決まりではなく、時には7回など、職人によって違いがあります。
粒がやや大きく、規則的な並びによって全体に華やかさとリズムが生まれます。晴れ着や訪問着に多く見られ、上品さと存在感を両立した模様として人気があります。
本疋田絞り
本疋田絞りは鹿の子絞りの中でも粒が細かい技法で、一粒に対して8回絹糸を巻いて括ることで仕上げられます。
とても緻密で整った模様が特徴で、仕上がりには繊細な立体感と優雅な雰囲気が生まれる点が人気を集める理由のひとつです。
疋田絞りよりもさらに細やかで、より高い技術を要するため、着物全体に気品を添える技法として知られ、熟練の職人により丁寧に施されます。
有松絞り・鳴海絞り
有松絞り・鳴海絞りは、愛知県名古屋市の有松・鳴海地区で江戸時代から続く伝統的な絞り染めの技法です。多彩な技法が存在し、その数はかつて100種類以上とも言われていました。
現在では約70種が継承されており、代表的なものに杢目縫い絞り、唐松絞り、雪花絞りがあります。以下でそれぞれの特徴を見てみましょう。
杢目縫い絞り
杢目縫い絞りは、生地に等間隔で線を描き、その線に沿って平縫いを施したのち、糸を強く絞って染色する技法です。
締めた部分には染料が入りにくくなり、縦に細かな筋模様が浮かび上がります。その模様が木の年輪や木目を思わせることから、この名前になりました。
使用する生地や糸の太さ、縫い目の大きさによって仕上がりの印象が変わり、個性的な印象を表現しやすい特徴があります。
唐松絞り
唐松絞りは、対称的な模様を作るために布を半分に折り、中心線に沿って外側へ向かって何本もの平縫いを施し、糸をしっかりと締めてから染色を行う技法です。
完成した模様が松ぼっくりのような形に見えることから、その名が付けられました。
基本は円形の配置が多く見られますが、縫い方や布の折り方を変えることで、違う形状に仕上げることもできます。
模様はひとつひとつが大きく存在感があり、華やかさと動きのある印象が生まれます。
浴衣やハンカチ・手ぬぐい、Tシャツなどの製作が主流となっております。
雪花絞り
雪花絞りは、「板締め絞り」と呼ばれる技法の一種で、染め上がった柄が雪の結晶のように見えることから、この名称がつけられました。
畳んだ布を木の板で挟み、紐でしっかりと固定してから染色する方法です。生地は主に三角形状に折りたたまれ、板の形と重なり方によって独特の模様が生まれます。
線と面が交差する幾何学的な文様が現れやすく、繊細で規則的な美しさが魅力です。
浴衣地として用いられることが多く、夏の装いに涼やかな印象を添える技法として親しまれています。
南部絞り
南部絞りは、秋田県や岩手県の南部地域で鎌倉時代から伝承されてきた絞り染めの技法で、古くから続く草木染の一種でもあります。植物の根を染料として用いるのが特徴で、使用する植物により染め色が変わります。
染め上がった生地には、絞りによる自然なムラが残り、それがかえって独特の風合いやぬくもりを引き立て、素朴な美しさとして愛されています。
たとえば、「紫根染」はキキョウに似たムラサキという多年草の根から得られる天然の紫色が特徴で、深みのある落ち着いた色合いに染まります。
「茜染」はアカネというつる性植物の根を使用して染められ、温かみのある赤みを帯びた色合いに仕上がります。
辻ヶ花絞り
辻ヶ花絞りは、室町から桃山時代にかけて流行した豪華な染色技法で、絞り染めに加え金彩、刺繍、描き絵などを組み合わせます。
「幻の染め」ともいわれ、一時は途絶えましたが、現代では再現技術が確立され芸術作品としての価値が見直されるようになりました。
美しい意匠は高級な着物や展示作品にも用いられ、その表現力の高さが支持され続けています。
嵐絞り
嵐絞りは、布を棒に巻き付けてから糸で強く締め付け、圧縮した状態で染料に浸すことで模様を作る絞り染めの技法です。
染め上がりには細く流れるような斜めの線が現れ、それがまるで荒天の雨脚のように見えることから「嵐絞り」と名付けられました。
技法そのものから「棒絞り」や「棒巻き絞り」と呼ばれることもあります。
作業工程によって模様の出方が変わるため、仕上がりには一点ごとの個性が表れます。
総絞りの着物の魅力

総絞りの着物は、布全体に絞り染めを施した繊細な意匠が魅力です。伝統的な職人技が凝縮されており、見た目の美しさだけでなく、着心地や格式の高さにも優れています。
ここでは、総絞りの着物が持つ特有の魅力について紹介します。
着心地がよい
総絞りは生地全体に細かく絞りを施しているため、表面に自然な凹凸が生まれます。この凹凸によって肌への密着が抑えられ、さらっとした軽やかな着心地が得られる点が特徴です。
また、生地に適度な伸縮性が加わることで動きやすさも増し、長時間の着用でも疲れにくいとされています。
高級感と品がある
総絞りの着物は、その製法自体が手間と時間を要する高度な技術に支えられています。一反の生地にいくつもの小さな絞りを施す作業は、職人による繊細な手作業の積み重ねです。
そのため、仕上がった着物は非常に高級感があり、絞りの密度や模様の整い方にも品格が漂います。
格式が求められる場でも着用できるものもあり、洗練された一着として支持されています。
華と個性が演出できる
総絞りはフォーマルにも洒落着にも対応できる柔軟さが、多くの着物愛好家から支持されています。
模様が全面に展開されるため、華やかな印象を与える一方、色彩や柄の構成次第で上品さや落ち着きを演出することも可能で、TPOに合わせた装いがしやすい点も魅力です。
全体に施された細かい絞りが独自の個性を引き立てるため、周囲とは一味違う装いを求める人にも好まれています。
まとめ
総絞りの着物は、布全体に施された絞り模様によってほかにはない風合いや存在感を生み出します。
高度な技術と時間を要することから、職人の手仕事の価値が詰まった一着となっており、見た目の華やかさだけでなく、着心地の良さや実用性も兼ね備えています。
また、模様や色合いの組み合わせによって上品にも個性的にも着こなせるため、フォーマルにもカジュアルにも対応できる汎用性の高さも魅力です。
株式会社辻和では絞りの着物についてもご相談いただけます。風合いや存在感、華やかさなど、絞りならではの魅力 がある着物をまとってみたいという方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
専任のコーディネーターがお話をお伺いして、お客様のご希望にぴったりの一枚をご用意いたします。